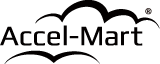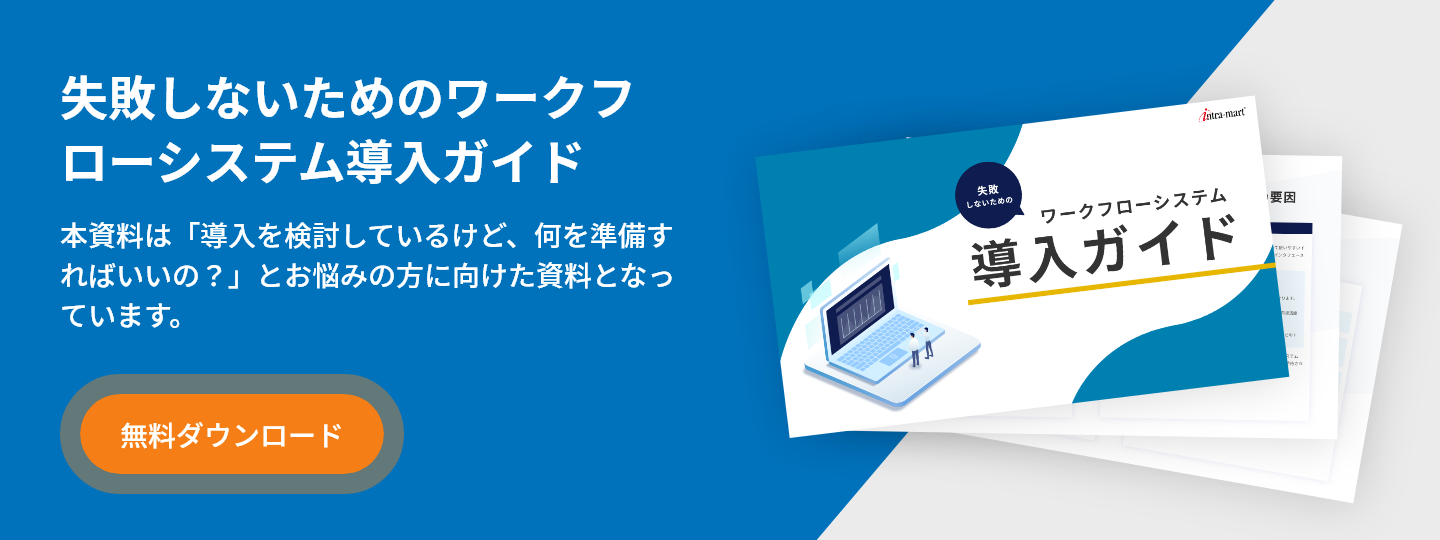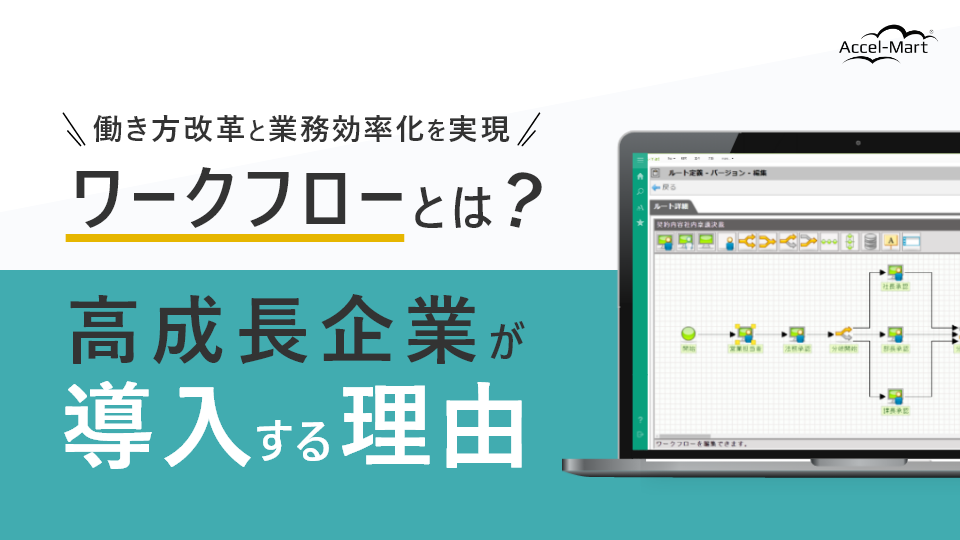ワークフローのリプレイスを行うべきタイミング
まず、ワークフローのリプレイスの流れは下記です。
- ステップ1.リプレイスのプロジェクトチームを立ち上げる
- ステップ2.移行計画書を作成する
- ステップ3.新ワークフローに求める要件を洗い出す
- ステップ4.予算を確保する
- ステップ5.新ワークフローを選定する
- ステップ6.新ワークフローをトライアル導入する
- ステップ7.新ワークフローを本導入する
- ステップ8.旧ワークフローを解約する
詳しくは「ワークフローのリプレイスの流れ」で説明しています。
では実際にどのような時にワークフローをリプレイスすべきなのか、最適なタイミングをお伝えします。
ワークフローのリプレイスを行うべきタイミングは、既存のワークフローでは解決できない課題が現れた時、もしくは、ワークフローにかかるコストを削減したい時です。
既存のワークフローでは解決できない課題が現れた時
導入当初はワークフローの使い勝手や機能が組織にぴったり合っていたとしても、時間の経過とともに生じる社内外の環境変化により、要件を満たさなくなるケースがあります。
たとえば、業務や従業員の人数の変化などが挙げられます。オンプレミス型のワークフローを利用していたが、運用を担当していた管理部門で大量退職があり、運用を継続できなくなったというケースもあるでしょう。
このような場合、機能追加やカスタマイズなど、既存のワークフローの拡張で対応できれば問題ありません。しかし、課題を解決できないなら、リプレイスを検討すべき時です。
ほかにも、ワークフローが古くなったりベンダーが倒産したりなどで保守が打ち切られた際も、リプレイスのタイミングです。
ワークフローにかかるコストを削減したい時
ワークフローの料金体系にも複数あります。導入時は最適なものを選んだとしても、時間が経って事情が変わり、高コストになってしまうケースもあります。
たとえば、ユーザー数に応じて課金される料金体系の場合、一定の人数を超えると高コストになってしまいます。また、買い切り型の料金体系では予算が確保できなくなり、月額制のワークフローに変えたいということも出てくるかもしれません。オンプレミス型で運用を自社で行っていた場合は、運用にかかる人件費を削減したいという理由で、運用費のかからないクラウド型に切り替えたいケースもあるでしょう。
このように、ワークフローにかかるコストを削減したい時もリプレイスのタイミングといえます。
ワークフローのリプレイスを行う前に準備すべきこと
上記のような状況になれば、リプレイスを検討する必要があります。
リプレイスを行う前に、以下の準備を整えておきましょう。
現状のワークフローを利用している部門を確認する
まずは、現状のワークフローを利用しているすべてのユーザー部門を、漏れなく把握する必要があります。
現状のワークフローで実施している業務や稟議を確認する
次に、ユーザー部門がどのような業務や稟議でワークフローを利用しているのか、実態を調査します。
実際にワークフローを使用している部門にヒアリングを行うことが望ましいでしょう。
現状のワークフローで生じている課題を把握する
現状のワークフローではなぜ問題なのか、生じている課題を具体的に把握する必要があります。実際にワークフローを使用している部門にヒアリングを行い、生じている課題を漏れなくピックアップしておきましょう。
さらに、要件に落とし込むために、どのような機能があれば解決するかを検討しておくと良いでしょう。
現状のワークフローの改善案を検討する
課題とは別に、そもそものワークフローをもっと効率化できないかも併せて検討しましょう。たとえば、省略できそうな申請・承認はないか、まとめられるタスクはないかといったことです。
改善案は、ワークフローを使用しているユーザー部門にも確認してもらい、現実的かどうかをチェックしてもらいましょう。
ワークフローのリプレイスの流れ
では、上記のような理由からワークフローをリプレイスしたい場合、どのような流れで実施すれば良いのでしょうか?
一般的に、以下の8ステップを踏むことでリプレイスが可能です。
1.リプレイスのプロジェクトチームを立ち上げる
まずは、リプレイスのプロジェクトを推進するチームを立ち上げましょう。情報システム部門などワークフローを管理する部門と、ユーザー部門との混成チームが望ましいです。
チームを編成と前後して、プロジェクトリーダーも選出しておきましょう。
2.移行計画書を作成する
移行計画書を作成します。移行計画書とは、リプレイスのスケジュールやリハーサル、移行するデータの範囲などを含め、誰がいつどのように移行を行うのかを記載したものです。
移行計画書には、移行概要やスケジュールのほか、予期せぬトラブルが発生した場合に備えたリカバリプランも記載して、元のワークフローに戻せるようにしておきましょう。
3.新ワークフローに求める要件を洗い出す
次に、現状のワークフローに生じている課題を洗い出し、新しいワークフローに求める要件を洗い出しましょう。忘れてはならないのが、既存のワークフローで実現できている要件も、新たなワークフローに引き継ぐ必要があるということです。
ただ、要件のすべてを満たせるワークフローが見つからない可能性もあります。優先度の低い要件は切り捨てられるよう、すべての要件を洗い出したら、優先順位を付けておきましょう。
これらの要件は、新しいワークフローのベンダーに共有すべき情報となります。
4.予算を確保する
社内の予算確保のフローに沿って、予算を確保します。個社ごとの予算確保プロセスによっては、順番を前後させて予算を確保してください。
後に選定するワークフローの種類によっても予算額は変わってくるでしょう。現状のワークフローにかかっている費用や、導入したいワークフローの料金について、この段階である程度、調べておく必要があります。
5.新ワークフローを選定する
既存のワークフローでは解決できない課題を解決できる、新しいワークフローを選びます。
まずは、「3.新ワークフローに求める要件を洗い出す」で明らかにした要件を備え、「4.予算を確保する」で決めた予算内に収まるものをピックアップしましょう。
さらに、「RFP(Request for Proposal/提案依頼書)」を作成して、候補先のベンダーに提出します。RFPを作る過程で依頼内容を整理できますし、ベンダーと自社の認識をすり合わせられ、プロジェクトの途中で判断に迷った時にも拠り所となります。
6.新ワークフローをトライアル導入する
選定した新ワークフローを、まずはトライアルで導入し、試してみましょう。
「3.新ワークフローに求める要件を洗い出す」で求める要件が揃っているか、操作性はどうかなどを実際に使ってみて判断します。プロジェクトチームを中心にユーザー部門にも使ってもらいましょう。期間の目安は、数週間から数ヵ月間です。
多くのワークフローでは、無料トライアル期間が用意されています。期間内で十分な確認ができなかった場合は、ベンダーにかけあってトライアル期間を延ばしてもらうと良いでしょう。
7.新ワークフローを本導入する
トライアル期間で導入に問題のないことを確認できれば、新ワークフローを契約して本格的に導入します。
移行計画書に沿ってデータ移行も実施し、リハーサルを経て、本稼働に移しましょう。
8.旧ワークフローを解約する
新ワークフローの稼働状況に問題に問題がなければ、旧ワークフローを解約し、リプレイスは終了です。
ワークフローのリプレイスを行う際のポイント・注意点
ワークフローをリプレイスする際は、以下の3点に注意しましょう。
旧ワークフローでの課題を解決できることを確認しておく
改めて言うまでもありませんが、リプレイスを行うのは旧ワークフローを利用し続けることで問題が生じているためであり、リプレイスによって解決することが目的です。新たなワークフローでは、旧ワークフローでの課題を解決できることを確認しましょう。
プロジェクトを進める中で、ユーザー部門の意見を聞いたり、ベンダーの提案を聴いたりするうちに、知らず知らずのうちに本質からそれていってしまうこともあるかもしれません。
そこで軸をブレさせないためにも、RFPを作成しておくことが大切です。
長く活用できるものを選ぶ
ワークフローのリプレイスは、手間も費用もかかる作業です。リプレイス後は長く使えるよう、長く活用できるものを選びましょう。
具体的には、使用する中で、ワークフローの変更・追加や、大がかりな組織変更などが生じる可能性も考慮し、柔軟性の高いワークフローであること。
また、機能追加やほかのシステムとの連携など、拡張性の高いものを選ぶことがポイントです。
新ワークフローでも操作講習を実施する
ワークフローの導入が初めての時は、ユーザー部門への操作講習に力を入れても、2回目、3回目ともなるリプレイスでは、「使えば、わかるだろう」とレクチャーを省略したくなるかもしれません。
しかし、機能や操作性の異なるワークフローを導入するのですから、慣れないユーザー部門にとっては、新しいシステムに触れるのと同じこと。新ワークフローでも、ベンダーに協力してもらいながら丁寧な操作講習を実施しましょう。
ワークフローのリプレイスの成功事例
最後に、ワークフローシステムのリプレイスに成功した事例を5つ、ご紹介いたします。
業務システムごとに乱立していたワークフローシステムをintra-martに集約
改修や機能追加のハードルも低下(三洋化成工業株式会社様)
界面活性剤などを主力製品とする化学メーカーである三洋化成工業では、ワークフローシステムが業務システムごとに自由に作り込まれている状態だったそうです。
このため、IT部門が担う運用保守業務も、ワークフローシステムごとに異なるルールと方法で行わなければならず、複雑化していたといいます。結果的に、運用保守が属人化する現状にありました。
一方で、もっと複雑なワークフローをシステム化して欲しいという要望も届いていましたが、実現できない状態でした。 中期経営計画で掲げるDX推進の一環として、ERPのリプレイスを検討しており、このタイミングで上記の課題を解消するため、ワークフローシステムとしてintra-martを導入しました。
業務システムごとに乱立していたワークフローをintra-martに集約したことで、ユーザーにとってはワークフローの操作性が統一され、使い勝手が向上したといいます。
さらに、intra-martはローコード開発プラットフォームであるため、ユーザーの要望を踏まえた改修や機能追加のハードルも下がったそうです。
事例の詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
SAP S/4HANAへの基幹システム刷新に伴う新フロントシステムに「intra-martR」を採用 ローコードとスクラッチの両輪で開発し、ワークフローシステム統合で利便性・保守性を向上
既存システムのサポート終了を機にintra-martへ移行
安定し稼働を続け、利便性も向上(オリックス生命保険株式会社様)
オリックス傘下の生命保険会社であるオリックス生命保険では、長年「Notes」を活用して部署や業務ごとに独自にシステムを整備してきたために、保守切れで対応が必要なシステムが乱立してしまっていることが課題でした。
グループウェア「Notes」のサポート終了に伴い、ワークフロー機能の移行先としてintra-martを採用。 部署ごとにサイロ化、肥大化していたワークフローシステムを、intra-mart上に集約し、約160の機能を再構築する方針を固め、移行を進めました。
移行プロジェクトの完了以降、不具合はなく安定した稼働を続けており、取材時点で、intra-mart上での月間申請数は2万1,000件を超えました。 intra-martにはポータルサイトがあるため、ユーザーが目的の申請を探すのも容易になり、利便性が向上したといいます。
事例の詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
ワークフローシステムの基盤をNotesから「intra-mart」へ移行 内製化を推進し、スクラッチだけでなく、ローコード開発ツールによるアプリ開発も選択肢に
業務ワークフローの構築先に「intra-mart」を採用
移行後のアンケートで90%以上の社員が業務負荷軽減を実感
(SOMPOホールディングス株式会社様)
SOMPOホールディングスでは、グループ全体でのDX推進の一環として、老朽化した「Notes」のリプレイスを検討していたといいます。
メールやチャットなどのコミュニケーション機能は米グーグルの「Google Workspace」へ移行、業務ワークフローの構築先に「intra-mart」を採用しました。
当初、ワークフロー以外の業務システムは、それぞれ別のシステムへの移行を検討していたそうですが、最終的に、同じローコード開発プラットフォーム上に移行することに。
移行後、業務システムの使い勝手についてアンケートを実施したところ、90%以上の社員が業務負荷軽減、80%以上の社員が業務品質向上を実感しているとの回答を得られたそうです。
事例の詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
SOMPOグループのNotesリプレイスを機に、ローコード開発基盤として「intra-martR」を採用 ビジネス部門とシステム部門の協創・アジャイル開発で関係社員の約90%が業務負荷軽減を実感
内製化により、外注コストを80%も削減
(Thai AirAsia Co., Ltd様)
タイ初のLCCとして、アジアを代表するマレーシアのエアアジアグループの一社であるタイ・エアアジア(Thai AirAsia)では、約3年間利用してきたワークフローシステム経費精算や購買業務等のさまざまな申請承認の処理を行っていました。
しかし、頻繁に変更が行われる組織変更やルール改定により、単なる承認ルートの変更だけでなく、業務プロセス自体の大幅な見直しに伴う根本的なワークフローの変更作業が常に平行して複数発生している状態だったといいます。
これらは、システムの仕様上、社内で対応できるものではなく、変更のたびに外注しており、費用も時間もかかっている点が問題でした。この間、ワークフローは紙ベースで行っていたそうです。 また、そもそも元のシステムの料金体系がユーザー課金制だったため、ユーザー数が6,000名を超える同社では、高コストとなっていました。
そこで、ワークフローの作成と変更が容易でコストパフォーマンスの良いシステムへのリプレイスを検討することに。ドラッグアンドドロップで一からワークフローのプロセスを作ることができる「intra-mart」を採用しました。
主に出張旅費精算をはじめとする社内のワークフロー業務に「intra-mart」を活用したところ、導入からわずか7ヵ月間で、内製により外注コストを80%削減、新規作成や変更の作業に要する時間の大幅な短縮を実現しました。
事例の詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
システムリプレースで業務プロセスの内製化を実現 従業員6,000名が利用する情報活用の基盤に
Webアプリケーション開発が初めてのメンバーを含むチームながら、
スピーディな移行に成功(三菱商事株式会社様)
総合商社である三菱商事では、世の中のオープン化の流れとともに、さらなるお客様・社内との情報連携強化のため、情報IT基盤の見直しに踏み切りました。
具体的には、Lotus Notes/Dominoから、SharePointとintra-martへの移行を決定。
特に、海外を含む全社利用のワークフローには、intra-martのクラウドサービス「Accel-Mart」を活用することを決めました。
開発を担当したのは、障がい者雇用の実現に向けて設立した三菱商事太陽のメンバー。
なかには、Webアプリケーション開発が初めてのメンバーもいたといいますが、メンバー同士の密な情報連携によってスピーディに遂行でき、新しい技術を習得できたことでモチベーションが上がったといいます。
移行後は、ユーザー側も違和感なく利用することができ、水準内のライセンスコストでコーポレートレベルでの統一感と固有の機能を補完できたといいます。
事例の詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
Lotus Notes/Dominoからの移行。 三菱商事6000名が利用する「ワークフロー/アプリケーション開発基盤」をintra-martで構築。
ワークフローの課題をリプレイスで解決しよう
既存のワークフローでは解決できない課題が生じたり、高コストになってしまったりしたら、リプレイスのタイミングです。
事前にユーザー部門にヒアリングを行って、現状のワークフローが抱える課題を把握し、解決できるワークフローにリプレイスしましょう。
リプレイスを成功させるためにも、現状のワークフローが抱える課題を解消でき、拡張性や柔軟性に優れたワークフローを選定すると良いでしょう。